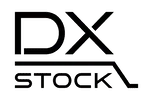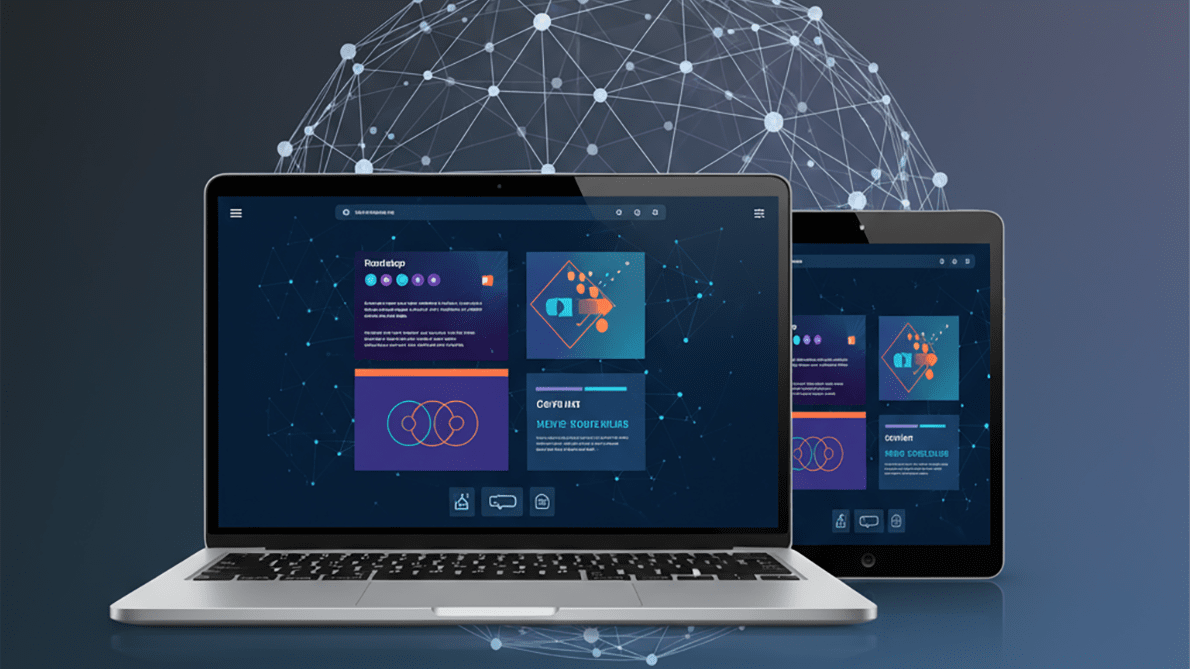人工知能の研究に強い大学はここ!研究室の実績やAI活用事例も紹介
まとめ

AI研究に強い大学の選び方
AI分野でトップレベルの大学を見極めるには、いくつかの重要な指標があります。偏差値や知名度だけでなく、より専門的な視点から大学の実力を見抜く方法を知っておきましょう。
国が認める質の証:文部科学省の教育プログラム
大学選びの信頼できる指標の一つが、文部科学省が推進する「数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム」です。このコンソーシアムに「拠点校」として選ばれている大学は、日本のAI教育をリードする役割を担っており、国からその教育水準や研究環境のお墨付きを得ていると言えます。
また、各大学が提供する教育プログラムの質を保証する「MDASH(マダッシュ)認定制度」も重要な判断材料です。この認定を受けている大学は、国が定めた基準を満たす体系的な教育を提供していることの証明になります。
世界的な評価を示す大学ランキング
大学の国際的な研究力を測るには、世界大学ランキングが参考になります。一般的な知名度を示す「QS世界大学ランキング」や「THE世界大学ランキング」のコンピュータサイエンス分野で常に上位にいる大学は、教育・研究ともに高いレベルにあると言えるでしょう。
さらに専門的な指標として、トップレベルの国際会議での論文発表数に基づく「CSRankings」があります。AIの最先端技術はこの種の会議で発表されることが多いため、このランキングは大学の「今」の研究力を非常に正確に反映しています。AIエンジニアを目指すなら、ぜひチェックしておきたい指標です。
AIを学ぶための学部・学科の選び方
AIを学ぶための代表的な学部・学科には、それぞれ特徴があります。
- 工学部(情報系): より応用的・工学的なアプローチで情報技術を学びます。AI技術を社会に実装することに興味がある人に向いています。
- 理学部(情報科学科): コンピュータサイエンスの根幹をなす、数理的・理論的な側面を深く探求します。アルゴリズムや計算理論など、AIの基礎を徹底的に学びたい人におすすめです。
- 情報学部: 工学・理学の枠を超え、より学際的に情報学を学びます。文理融合的なアプローチで、人間の心理や社会と情報技術の関係などを探求できる大学もあります。
自分の興味が「技術で何を作るか」にあるのか、「技術そのものを深く理解するか」にあるのかを考えることで、最適な学部・学科が見えてくるでしょう。
AIの主な研究分野と活用事例
大学では、AIに関する様々な分野の研究が行われています。ここでは代表的なものをいくつか紹介します。
研究分野 | 概要 | 主な活用事例 |
|---|---|---|
機械学習 | データからパターンやルールを自動で学習する技術。AIの中核をなす。 | 株価予測、迷惑メールフィルタ、医療画像診断支援 |
コンピュータビジョン | 画像や動画をコンピュータに認識・理解させる技術。 | 自動運転車の障害物検知、顔認証システム、製品の異常検知 |
自然言語処理(NLP) | 人間が日常的に使う言葉(自然言語)をコンピュータに処理させる技術。 | 機械翻訳、チャットボット、文章の自動要約 |
ロボティクス | ロボットの設計、制御、知能化に関する研究。 | 産業用ロボット、災害救助ロボット、家庭用お掃除ロボット |
AI・人工知能の研究に強い大学5選
それでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、AI研究で特に評価の高い日本のトップ大学を5校紹介します。
東京大学 工学部 (電子情報工学科・機械情報工学科)、理学部 (情報科学科)
名実ともに日本のトップであり、AI研究においても世界をリードする存在です。文部科学省の拠点校であり、各種コンピュータサイエンスランキングでも常に国内1位にランクされています。工学部は応用、理学部は理論と、多様なアプローチでAIを深く学べる環境が整っています。
著名な研究室
- 松尾・岩澤研究室: 日本のAI研究を語る上で欠かせない中心的な研究室です。深層学習(ディープラーニング)や生成AIの最先端テーマに取り組み、数多くのAIスタートアップを輩出しています。
- 杉山・横矢・石田研究室: 機械学習の基礎理論における世界的権威である杉山将教授が率いています。信頼できるAIの構築に不可欠な基盤技術を研究しています。
京都大学 工学部 (情報学科)
東京大学と並び称される最高学府で、独創的な研究文化で知られています。工学部情報学科では、数学と物理学を基礎として情報の本質を究明し、計算機科学から人工知能まで広範な領域をカバーしています。
著名な研究室
- 鹿島・竹内研究室: 機械学習とデータマイニングの第一人者である鹿島久嗣教授が主宰。複雑なデータを扱う機械学習や、それを用いた意思決定支援の研究で知られています。
- 河原研究室: 音声認識や対話システム、自然言語処理の分野で著名な研究室です。企業との共同研究も活発で、実用的な研究成果を数多く生み出しています。
東京科学大学 情報理工学院 (数理・計算科学系、情報工学系)
日本最高峰の理工系総合大学であり、その研究力は世界トップクラスです。全学生を対象としたデータサイエンス・AIの体系的な教育プログラムを提供しており、学問の垣根を越えてAIを学べる環境が大きな特徴です。2024年10月からは「東京科学大学」として新たなスタートを切ります。
著名な研究室
- 岡崎研究室: 自然言語処理(NLP)分野の世界的権威である岡崎直観教授が率いています。高性能な日本語大規模言語モデルの開発など、日本のNLP研究を牽引する存在です。
- 山田誠二研究室: 人間と協調するAIパートナーの実現を目指し、ヒューマンエージェントインタラクションの研究を行っています。
東北大学 工学部 (電気情報物理工学科)
研究を重視する伝統を持つトップ大学です。工学部の情報工学コースでは、コンピュータシステムの基礎技術から、知能ロボット、ビッグデータ科学、AIといった最先端の応用までを体系的に学ぶことができます。
著名な研究室
- 坂口・乾研究室: 日本を代表する自然言語処理(NLP)の研究グループの一つです。言語の深い理解や対話システムなど、知的な言語処理の根幹に関わる研究で世界をリードしています。
- 大関・工藤研究室: 量子コンピューティングをAIに応用するなど、次世代の計算技術に関する先進的な研究を行っており、大学の未来志向を象徴しています。
大阪大学 工学部 (電子情報工学科)、基礎工学部 (システム科学科)
西日本を代表する研究大学であり、コンピュータサイエンス分野でも常に上位に位置しています。工学部ではAIに直結する内容を、基礎工学部では数学を基盤としたAIやロボット工学に焦点を当てたユニークな教育を行っています。
著名な研究室
- 清水研究室: データから原因と結果の関係性を探る因果推論AI(Causal AI)など自然現象や人間行動の根底にある因果メカニズムをデータに基づいて解明するための数理的方法論に関する研究を行っています。
大学によるAI活用事例
北陸先端科学技術大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)は、最先端の科学技術に関する大学院教育を行う国立大学です。特にAI(人工知能)分野においては、研究、教育、そして社会実装の各側面で特色ある取り組みを推進しています。
JAISTは、社会のニーズに応える高度なAI人材を育成するため、特色ある教育プログラムを提供しています。
2024年度に文部科学省の「大学・高専機能強化支援事業」の採択を受け、2025年度10月から「高度情報専門人材育成コース(JAIST×Humanコース)」を開始します。本コースは、AI、インタラクション、サイバーセキュリティ、ヒューマンの4分野を複合的に学ぶユニークなカリキュラムが特徴です。AI倫理などを共通の必修科目とし、人間とAIが共生する社会における次世代AI(人間中心AIや解釈可能AIなど)の研究開発を担う人材の育成を目指しています。
また、一般社団法人JAIST支援機構が運営する「JAIST産学官共創フォーラム」では、「データサイエンス共創研究会」や「デジタルナレッジツイン研究会」といったテーマ別の研究会を複数設置しています。これらの研究会では、参加企業が持ち寄った実際のビジネス課題に対し、JAISTの教員や学生が専門的知見を提供し、生成AIなどを活用しながら共同で解決策を探求します。異業種の参加者との「共創」を通じて、実践的な問題解決能力を養う場となっています。
参考文献(検証日:2025年8月5日)
東京外国語大学
東京外国語大学は、その卓越した言語教育と多文化研究の伝統を基盤に、AI(人工知能)技術の活用を多角的に推進しています。特に「言語」という専門性を核に据え、教育、研究、そして大学運営のDX(デジタルトランスフォーメーション)において特色ある取り組みを展開しています。
2025年4月には「本学におけるAIの業務利用に関するガイドライン」を策定し、教職員がAIを業務で利用する際の原則と指針を明確化しました。
また、2025年度の年次計画においては、多言語でのメディア発信事業「日本語で読む世界のメディア」において、生成AIを活用した独習法の改善や、授業での活用法を検討することが盛り込まれています。
このように、東京外国語大学は、AIを単なる技術として捉えるのではなく、言語教育と研究を深化させ、グローバルな知の共創を加速するための重要なパートナーとして位置づけ、その活用を積極的に推進しています。
参考文献(検証日:2025年8月5日):
大阪教育大学
大阪教育大学は、教員養成大学としての特性を活かし、教育現場におけるAIの適正な利活用に重点を置いています。特に、三田市教育委員会との共同研究で開発したAI対話アプリ「MIRAIノート」の取り組みが注目されます。
このアプリは、不登校の児童生徒や若手教員のコミュニケーション支援などを目的に開発され、現場での実証研究が進められています。
また、授業におけるAI活用として、サーマルカメラと画像認識で学習者の行動を分析する研究や、AIを用いた意見共有システムによる効果的なグループ分けの実践なども行っており、教育の質向上を目指した多角的なアプローチを展開しています。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- AI対話アプリ「MIRAIノート」の成果報告会を開催 - 大阪教育大学
- 生成AIを活用した中学生の新しいスポーツ習慣支援事業 - Sport in Life
- 数理・データサイエンス・AI教育プログラム | 国立大学法人 大阪教育大学
- 生成系AIの使用に関する留意事項について | お知らせ - 大阪教育大学
- サーマルカメラを用いて教室全体の状況をAIが「見える化」 産学連携による実証実験&研究成果 記者発表のご案内 | お知らせ - 大阪教育大学
- 自然科学コースの授業でAIを活用したグルーピングを試行 - 大阪教育大学
- 「AIを用いた意見共有システムの教育活用」をテーマに 全学FD事業を実施 - 大阪教育大学
明治大学
明治大学は、2024年4月から全学生・教職員約3万6000人を対象に、マイクロソフト社の「Azure OpenAI Service」を基盤とした対話型AIサービス「M-Chat」の提供を開始しました。
このサービスは、入力した情報がAIの学習に利用されることのない、セキュリティが確保された環境で「GPT-4」などを利用できる点が最大の特徴です。
レポート作成や研究におけるアイデア創出、プログラミング支援など、教育・研究活動の質の向上と業務効率化を目的としており、全学的なAI活用を推進しています。
参考文献(検証日:2025年8月6日):
武蔵野美術大学
武蔵野美術大学は、美術大学としての教育哲学に基づき、生成AIとの向き合い方を明確に示しています。2023年5月には、国内大学でも早期に学長メッセージとして公式見解を公表しました。
その中で、AIを単なる効率化の道具と捉えるのではなく、思考を深める「対話の相手」や、新たな表現を生む「創造の道具」として主体的に活用する重要性を強調しています。
また、2025年7月には、株式会社はてなと共同で、生成AIを用いた発話分析ソリューション「toitta」の言語処理精度を向上させるプロジェクトを開始。ユーザーインタビューの分析プロセス支援など、具体的な研究開発にも着手しています。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
京都芸術大学
京都芸術大学は、学生の学習支援を目的とした対話型AI「Neighbuddy(ネイバディ)」を独自開発し、2024年秋から一部の授業で試験的に導入しています。
このAIは、学生が記録した授業ノートや過去の対話履歴を基に、個々の学生に合わせた復習や探求学習をサポートする「学びの相棒」として機能します。アンケートでは、利用学生の85.9%が継続利用を希望しており、個別最適な学習環境の実現に向けた活用が期待されています。
今後は協力学生と共に検証を重ね、教育現場での本格的な実用化を目指しています。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- 利用継続希望85.9% ― 京都芸術大学、学習特化AI『Neighbuddy』で教育の個別最適化に挑戦
- 京都芸術大の学習特化AI「Neighbuddy」実用化へ期待
- 共に学びを深める!AIを活用した「スタートアップ思考」の授業 | クロステックデザインコース | KUA BLOG - 京都芸術大学
信州大学
信州大学は、全学的なAI利用環境の整備と、各学部の専門性を活かした応用研究の両輪でAI活用を推進しています。2025年4月には、株式会社スリーシェイクと共同で「AI開発人材育成プログラム共同研究部門」を設置しました。
この共同研究部門では、学生や社会人を対象に、専門領域とAI技術を融合して新たなビジネスを創出できる人材の育成を目指しています。特に、医療・ヘルスケア分野などでの実践的なスキル習得を重視しています。
また、農学部ではドローンとAIで苗木の生育状況を自動確認するシステムを国内で初めて開発するなど、各分野での先進的な取り組みも進めており、AI時代に対応した人材育成と社会実装に力を入れています。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- 【学生・教員の皆さんへ】信州大学の学修・教育におけるAI活用に関するガイドラインについて
- スリーシェイク、信州大学と共同で「AI開発人材育成プログラム共同研究部門」を新設 | 3-shake
- ICT・AI技術を活用したスマート精密林業が日本の林業を変える。 - 信州大学
- 信州大学発スタートアップ認定企業特集10 AIで人の可能性を拡張したい、若き起業家の挑戦
- 信州大学で生成AI講座を実施、「実用性の高さ」に驚きの声 TIMEWELL - こどもとIT
駒澤大学
駒澤大学は、大学運営の中核である事務業務に生成AIを本格導入し、業務の効率化と高度化を全学的に推進しています。2025年4月には、Googleの生成AIサービス「Gemini Education」を事務業務に導入しました。
この取り組みは、議事録の作成支援、各種文書の要約、アンケート分析などにAIを活用することで業務負担を軽減し、創出された時間を学生への教育・支援といった本来の業務に充てることを目的としています。
学内では「AI推進プロジェクト(K-AI)」が組織され、職員を対象とした活用セミナーを積極的に開催するなど、単なるシステム導入に留まらず、全学的なAIリテラシーの向上と組織的な活用促進を図っている点が特徴です。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- 駒澤大学が事務業務にGoogleの生成AIサービス「Gemini Education」を導入~Google Workspace for Educationを基盤として活かし、生成AIをより身近なツールに~ - 大学プレスセンター
- 駒澤大学、事務業務にGoogleの生成AIサービス「Gemini Education」を導入 | ICT教育ニュース
- 駒澤大学がGoogleの生成AIサービス「Gemini Education」を導入、業務効率化と質向上を目指す
- AI推進プロジェクト(K-AI)による「Gemini活用スタートアップセミナー」が開催されました - 駒澤大学
岡山大学
岡山大学は、医療分野におけるAIの応用研究で国内をリードしています。特に、株式会社両備システムズと共同開発したAI診断支援システムの社会実装が注目されます。
2024年4月には、AIを用いて早期胃癌の深達度診断を支援するシステムが、国内で初めて医療機器として製造販売承認を取得しました。また、診断が困難であった胆道がんの病変範囲をAIで明瞭化する診断支援技術も国内で初めて開発するなど、難治性がんの診断精度向上に大きく貢献しています。
さらに、患者のメンタルケアを目的とした対話型AI や、介護保険制度を説明する生成AIチャットボット の開発も行っており、医療現場のあらゆる課題解決にAI技術を応用しています。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- 岡山大学と両備システムズが開発した早期胃癌の深達度をAIで診断支援するシステムが、医療機器製造販売承認を国内で初めて取得 - 株式会社両備システムズ
- 岡山大学と両備システムズがAIを活用した医療技術革新に挑む - 大阪Days ニュース
- 国内初!生成AIチャットボットによる介護保険説明で理解をサポート! - 国立大学法人 岡山大学
- 岡山大学と両備システムズ、早期胃がんの深達度を判定するAIを開発 - ZDNET Japan
- 国内初、岡山大学病院と両備システムズが胆道がんをAIで診断支援するシステムを開発 - AIsmiley
- AIを活用したメンタルケアサポートシステムを開発~患者さんとの対話で心に寄り添うAI~ - 国立大学法人 岡山大学
関西大学
関西大学は、全学的なAI利用基盤の整備と、各学部における専門教育への応用を両輪で進めています。2023年4月には、生成AIの教育利用に関する基本方針を早期に提示し、安全かつ効果的な活用に向けた姿勢を明確にしました。
大学としては、文部科学省の認定制度に対応した「AI・データサイエンス教育プログラム」を全学的に展開。学生がAIを使いこなすための基礎的な能力を育成しています。
学部単位の取り組みとしては、総合情報学部がホームページにAIチャットボットを導入し、学生からの問い合わせに自動応答するシステムを運用。また、商学部でも独自のAI・データサイエンス教育プログラムを設け、ビジネス分野における実践的なデータ活用能力の育成に力を入れています。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- AIを活用したチャットボットシステムを導入しました - 関西大学
- AI・データサイエンス教育プログラム - 関西大学
- 教育・学習におけるChatGPT等の生成系AIツー…|最新情報 一覧 - 関西大学
- 商学部AI・データサイエンス教育プログラム - 関西大学
- AI活用人材育成プログラム - 関西学院大学
- ロボットが人のホントを見抜いてる~センシング・AI技術の可能性 - 関西大学
- 教育・学習におけるChatGPT等の生成系AIツー…|最新情報 一覧 - 関西大学
大阪学院大学
大阪学院大学は、全学的なAIリテラシー教育の基盤整備に力を入れています。2023年度から、文系学生も含む全学生を対象とした「OGU数理・データサイエンス・AI教育プログラム」を開始しました。
このプログラムは、「AI活用入門」などの科目を設け、学生がAIの基礎知識や活用法、倫理的な留意点を体系的に学ぶことを目的としています。これにより、AIを主体的に使いこなせる人材の育成を目指しています。
また、生成AIの利用については一律に禁止するのではなく、各授業担当者の指示のもとで適切に利活用することを促す基本方針を2023年7月に示しており、教育現場におけるAIとの共存を模索しています。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- ChatGPTなどの生成AIの利用について(在学生の皆さんへ) | NEWS | 大阪学院大学 - OGU
- OGU数理・データサイエンス・AI教育プログラム | 教育情報の公開 - 大阪学院大学
- 【対象:23 年度以降入学生】 「OGU 数理・データサイエンス・AI 教育プログラム」について
- 「OGU 数理・データサイエンス・AI 教育プログラム」自己点検評価・報告書 - 大阪学院大学
近畿大学
近畿大学は、学生サービス向上と大学運営の効率化を目的として、多様なAIソリューションを実践的に導入しています。
2024年10月には、生成AIと連携した高精度チャットボット「SELFBOT」を導入。ドキュメントやURLを自動学習し、学生からの問い合わせに24時間体制で柔軟に対応することで、窓口業務の負担を大幅に軽減しています。
さらに、2025年2月からはAIを活用した「落とし物クラウドfind」を導入し、学生がLINEで手軽に落とし物を検索できるサービスを提供。事務業務においても生成AIプラットフォーム「Graffer AI Studio」を試験導入するなど、多角的なアプローチでAIの社会実装を進めています。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- 大学で生成AIを活用する事例10選!メリットや導入のポイントを解説
- 生成AI連携の「SELFBOT」導入で、近畿大学のAIチャットボットが進化 - SELF (セルフ)株式会社
- 近畿大学、AIを活用した落とし物検索サービス「落とし物クラウドfind」を導入 - AIsmiley
- 近畿大学、高精度チャットボット「SELFBOT」を新たに導入 - こどもとIT
- 近畿大学、窓口業務に生成AI搭載チャットボット「SELFBOT」を導入--教職員の負担を軽減 - ZDNET Japan
- 近畿大学が生成AI活用プラットフォーム「Graffer AI Studio」を導入 - PR TIMES
- 近畿大学、生成AI連携チャットボット「SELFBOT」導入で学生からの問い合わせ対応チャットボットを進化 - EdTechZine
明治学院大学
明治学院大学は、全学的な「AI・データサイエンス教育プログラム」を基盤とし、学生による創造的なAI研究の推進において顕著な成果を上げています。
このプログラムを履修する学生グループの研究「生成AIを活用した顔表情からの表情コピーと感情マップ生成」が、日本顔学会の「フォーラム顔学2024」にて輿水賞を受賞しました。この賞は、その着想と構想が顔学構築に大きなインパクトを与える研究に贈られるものです。
本研究は、生成AI技術を用いて個人に特化した感情マップを生成し、高精度な感情推定の実現を目指すもの。AI教育が、学生主体の先進的な文理融合研究へと結実した好事例です。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- 学生グループによる研究「生成AIを活用した顔表情からの表情コピーと感情マップ生成」がフォーラム顔学2024にて輿水賞を受賞しました - 明治学院大学
- AI・データサイエンス 教育プログラム - 明治学院大学
- 生成AIを活用した感情マップで個人の 「顔表情からの感情推定」が可能に ~明治学院大学「AI・データサイエンス教育プログラム」の 学生グループが日本顔学会輿水賞を受賞 - アットプレス
- 明治学院大学 情報数理学部 情報数理学科 情報と数理の力で人が主役のAI社会を創る。
- ChatGPTの使用について/Use of ChatGPT - Meiji Gakuin University
広島大学
広島大学は、産学連携によるAIアプリケーションの共同開発と、それを支える先進的な情報基盤の構築を両輪で進めています。
特筆すべきは、ソフトバンクと共同で開発する遠隔授業AI学習支援アプリ「TSUNAGU」です。このアプリは、地域や言語の壁を越えて、全ての子どもたちが共に学び合う新たな教育の形を目指すもので、2025年6月に発表されました。
また、NetAppやAWSと連携し、オンプレミスとクラウドを組み合わせたハイブリッド環境を構築。機密性の高い研究データを安全に管理しつつ、将来的には独自のデータを活用した生成AI(RAG)の導入を目指しており、次世代の研究・教育基盤を戦略的に整備しています。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- 広島大学の導入事例 - Google Cloud
- NetAppとAWS-広島大学との実証実験
- 生成AIの活用 - 広島大学
- 【遠隔授業AI学習支援アプリ”TSUNAGU(仮称)”】ソフトバンクとの共同開発するAIシステムがソフトバンクニュースに掲載されました!(2025.06.26) - デジタル・シティズンシップ・シティ - 広島大学
- NetAppとAWS-広島大学との実証実験
京都産業大学
京都産業大学は、大学DX推進の中核施策として、2024年3月からAIチャットボット「PKSHA AI Helpdesk for Microsoft Teams」を全国の大学で初めて全学的に導入しました。
このシステムは、学生・教職員からの問い合わせ対応を効率化するもので、日常的に利用するMicrosoft Teams上にAI窓口を設置している点が特徴です。
AIで回答できない質問は職員によるチャット対応に切り替わり、その応答ログをAIが自動で学習してFAQを生成するため、人とAIが協働しながら継続的に回答精度を高める仕組みを構築しています。これにより、学生の利便性向上と窓口業務の効率化を同時に実現しています。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- 大学DX - 京都産業大学
- グランドデザイン | 大学の取組み - 京都産業大学
- PKSHA、大学DXに向けて京都産業大にPKSHA AI ヘルプデスクを導入 - PR TIMES
- 京都産業大、大学DXに向けてAIヘルプデスクを導入
- 【京都産業大学】全国の大学で初めて!全学的にPKSHA AI ヘルプデスク for Microsoft Teamsを導入!学生の成長のための「大学DX」を推進 - 大学プレスセンター
多摩美術大学
多摩美術大学は、AIを単なる技術としてではなく、デザインやアートの新たな可能性を探る知的探求の対象と位置づけ、研究プラットフォームを核とした活動を展開しています。
同大学は、東京ミッドタウン・デザインハブ内の拠点「TUB」をベースに、「Tama Design University」プロジェクトを始動。研究テーマの一つに「AIとデザイン」を掲げ、美術大学の視点からAIを考える活動を続けています。
このプラットフォームでは、情報デザイン学科や統合デザイン学科をはじめとした、複数の学科の教員や学生が横断的に関わり、各界の専門家や企業と連携しながらシンポジウムやワークショップを実施。AI時代の創造性のあり方を根源から問い直し、その成果を広く社会に還元する取り組みを進めています。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- 多摩美術大学、AIやサーキュラーなど5つの最先端のテーマを研究するプラットフォームをスタート - PR TIMES
- 多摩美術大学がAIやサーキュラーなど5つの最先端のテーマを研究するプラットフォームをスタート - 美術手帖
- division of AI & DESIGN - 多摩美術大学 TUB
沖縄科学技術大学院大学
沖縄科学技術大学院大学(OIST)は、世界トップレベルの基礎科学研究において、AIを不可欠な探求のパートナーとして活用し、新たな科学的発見を追求しています。
特筆すべきは、人間やAI単独では解明できなかった量子物理学の難問に対し、両者の協働によって解決を図る研究です。2025年7月には、このアプローチによって量子物質の未知の相を特定することに成功したと発表しました。
また、NTTと連携してサステナブルなAI社会の実現を目指す包括的な研究や、脳の仕組みに着想を得た「脳型AI」の開発など、学際的な環境でAIを駆使した最先端の研究を推進しています。
参考文献(検証日:2025年8月7日):
- 人間だけでもAIだけでも解けなかった量子物理の問題を共に解決 - OIST
- サステナブルなAI社会の実現をめざして、NTTと包括的な研究連携に合意 - OIST
- 統合プラットフォームでグローバル規模のイノベーションを実現、沖縄科学技術大学院大学 - ServiceNow
- New, embodied AI reveals how robots and toddlers learn to understand - OIST
- Human-AI 'collaboration' makes it simpler to solve quantum physics problems - OIST
八洲学園大学
八洲学園大学は、生涯学習を支援する通信制大学としての特性を活かし、社会人が実践的にAIを活用するための教育プログラムを提供しています。
その代表例が、公開講座として新規に開講された「つくることが苦手な人のための、自分のやりたいことを生成AI を活用して試しにつくってみる入門講座」です。この講座は、専門的な知識がない学習者を対象に、生成AIを用いてアイデアを具現化するスキルを育成することを目的としています。
参考文献(検証日:2025年9月22日):
聖徳大学
聖徳大学は、AIの活用スキルを実践的に学ぶ機会の提供に注力しています。その代表例が、学生や社会人を対象に開講するオープンセミナー「ChatGPTを使って誰でもできる」です。
この講座では、専門知識がない参加者でも生成AIを用いて簡単なアプリケーション制作を体験できるよう設計されており、AIを創造的に活用するスキルの育成を目的としています。
こうした実践的な学びの場に加え、全学生を対象とした「ソーシャルデータサイエンス・AIリテラシープログラム」を設置。AIを社会で責任をもって活用できる人材を育成するため、体系的な教育基盤も整備しています。
参考文献(検証日:2025年9月22日):