クラウドPBXの音質比較ガイド|サービスの選び方と安定した環境の作り方を解説
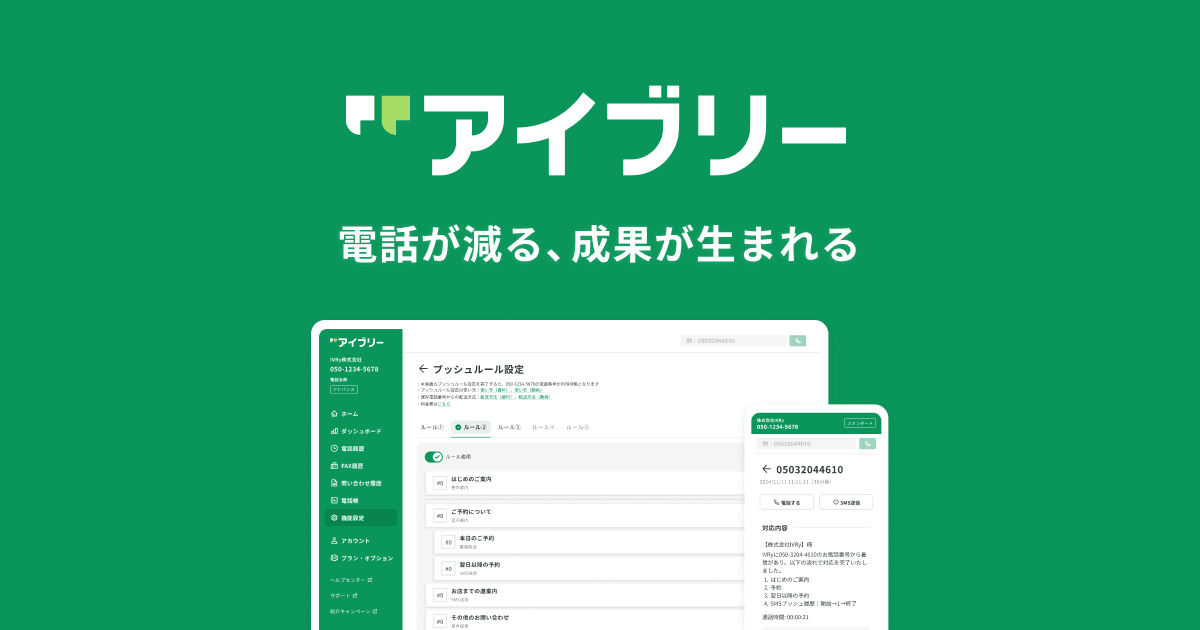
クラウドPBXは、従来のビジネスフォンに代わる柔軟でコスト効率の高い選択肢として、多くの企業で導入が進んでいます。しかし、インターネット回線を利用するため、「通話品質は本当に安定しているのか」「顧客との重要な通話に支障はないか」といった懸念を持つ方も少なくありません。
実際に、クラウドPBXの音質は利用するサービスや自社のネットワーク環境によって大きく左右されるのが事実です。
本記事では、クラウドPBXの音質が変動する仕組みから、品質を客観的に評価するための指標、安定した通話品質を実現する環境要件、そして音質とコストのバランスが取れたサービスの選び方まで、専門的な視点で徹底的に解説します。
クラウドPBXの音質が安定しない理由
クラウドPBXの通話品質を理解するために、まずは音質が不安定になる理由から見ていきましょう。従来のビジネスフォンとは異なり、クラウドPBXの音質は、利用者のネットワーク環境や音声圧縮技術(コーデック)など、複数の要因に影響されます。
音質を左右するネットワーク環境とコーデック
クラウドPBXは、インターネット経由で音声データをやり取りするため、利用するインターネット回線の品質がそのまま通話品質に直結します。例えば、回線が混雑していたり、Wi-Fiの電波が不安定だったりすると、音声が途切れたり、遅延したりする原因になります。
また、「コーデック」と呼ばれる、音声データをデジタルに変換・圧縮する技術も音質を左右する重要な要素です。高音質なコーデック(例: G.711)は多くのデータ量を必要とする一方、圧縮率の高いコーデック(例: G.729)は少ないデータ量で済みますが、音質は若干劣ります。最近では、ネットワーク状況に応じて音質とデータ量を最適化する、高機能なコーデック(例: Opus)も登場しています。
このように、クラウドPBXの音質はサービス提供側の設備だけでなく、利用者側のインターネット環境や、サービスが採用している技術によって大きく変動します。
クラウドPBXで高品質な通話ができる仕組み
クラウドPBXはインターネットを利用するため品質が変動しやすい一方、適切な環境とサービスを選べば、固定電話と遜色ない、あるいはそれ以上にクリアな通話を実現できます。
高品質な通話を可能にするのが、サービス提供者の堅牢なインフラと、利用者側で設定できる「QoS(Quality of Service)」です。信頼できる事業者は、国内の複数拠点にデータセンターを分散させるなど、安定したサービス提供に努めています。
さらに、利用者側のルーターなどでQoS設定を行えば、��音声データを他のデータ通信よりも優先的に処理させることが可能です。これにより、ネットワークが混雑している状況でも音声の遅延や途切れを防ぎ、安定した通話品質を確保できます。
アナログ回線とクラウドPBXの通話品質の違い
アナログ回線(固定電話)は、通話時に物理的な回線を1対1で占有するため、音質が安定しているのが特徴です。
一方、クラウドPBXは複数の通信が共有するインターネット回線を使うため、そのままでは品質が不安定になる可能性があります。
しかし、前述したQoS技術の活用や、広帯域で安定した光回線を利用することで、クラウドPBXでもアナログ回線と同等、もしくはそれ以上の高品質な通話を実現できます。最新の音声技術の恩恵を受けられるため、ノイズの少ないクリアな音声になることも少なくありません。
クラウドPBXの音質を評価する客観的な指標
クラウドPBXの音質は主観的に「良い」「悪い」と判断されがちですが、品質を客観的に評価するための統一された指標が存在します。サービスを選定する際にはこれらの指標を参考にすることで、より正確に比較検討できます。
総務省の「IP電話の音声品質基準」
日本国内のIP電話サービス(クラウドPBXを含む)には、総務省が定めた音声品質の基準があります。この基準はサービスの品質を3つのクラスに分類しており、多くの事業者が品質レベルを示す客観的な指標として用いています。
クラス | 品質の目安 | 相当するMOS値 |
|---|---|---|
クラスA | 固定電話と同等の最高品質 | 4.0以上 |
クラスB | 携帯電話と同等の通常品質 | 3.1以上 |
クラスC | 携帯電話を下回る品質 | 2.6以上 |
クラウドPBXを選ぶ上で明確な基準となるのが、「クラスA」を獲得しているかどうかです。 これは、サービスが固定電話と同等の高品質な通話を提供する能力を持っている証明になります。
R値
R値(R-value)は、遅延、ノイズ、エコーといった複数の品質要因を総合的に計算し、通話品質を0〜100の数値で示す評価指標です。数値が高いほど品質は良いとされ、一般的にR値が80以上であれば多くのユーザーが満足する品質レベルとされています。
MOS値(Mean Opinion Score)
MOS値は、実際に人間が音声品質を聴き、「非常に良い(5)」から「非常に悪い(1)」までの5段階で評価した主観評価の平均値です。R値が計算上の理論値であるのに対し、MOS値はより実際の「聞こえ方」に近い指標と言えます。
ビジネス利用においては、MOS値4.0以上が「高品質」、3.5以上で「問題ない品質」と判断するのが一般的です。 先進的なサービスでは、管理画面から各通話のMOS値を確認できるものもあり、品質のモニタリングに役立ちます。
PESQ(Perceptual Evaluation of Speech Quality)
PESQは、元の音声とネットワーク伝送後の音声をアルゴリズムで比較し、品質の劣化度を客観的に測定する手法です。MOS値と高い相関があり、より自動的かつ客観的に品質を評価するために利用されます。
総務省の品質基準で「クラスA」認定のクラウドPBX
顧客との通話で高い品質を確保したい場合、総務省の品質基準で「クラスA」を獲得しているサービスを選ぶことが重要な判断基準となります。ここでは、クラスA評価を公式に発表している代表的なサービスをいく�つか紹介します。
モバビジ
「モバビジ」は、固定電話と変わらない高い通話品質を強みとするクラウドPBXサービスの一つです。総務省の通話品質基準でクラスAを獲得しており、安定した通信環境を提供しています。
VoiceX
「VoiceX」も、総務省の品質基準でクラスA評価を受けているサービスです。特に、低コストで高品質な通話を実現できるプランを提供しており、コストパフォーマンスを重視する企業にも適しています。
CLOUD PHONE
「CLOUD PHONE」もまた、クラスAの品質基準をクリアしていると公表しているサービスです。ユーザー数に応じたシンプルな料金体系で、高品質な通話を低価格から利用できる点が特徴です。
音質とコストで比較する際の選定ポイント
クラウドPBXを選ぶ際は、単に「音質が良い」という評判だけでなく、客観的な指標と自社の利用環境を照らし合わせて判断することが不可欠です。
まず、総務省の「クラスA」評価を品質のベースラインとして確認した上で、各社の料金プランを比較検討しましょう。多くのサービスが無料トライアルを提供しているため、必ず実際の業務環境でテスト利用し、本当の「聞こえ方」を確認することが、失敗しないための最も重要なポイントです。
また、安定した品質を確保するには、自社のネットワーク環境(光回線の導入やQoS設定)の見直しも同時に進める必要があります。音質・コスト・自社環境の3つのバランスが取れたサービスこそが、最適な選択肢となります。
クラウドPBXの導入を検討中なら「アイブリー」がおすすめ
「アイブリー」は、IVRを活用したクラウド型の電話自動応答サービスです。電話の着信時に自動音声ガイダンスが応答し、用件に応じて音声案内や転送を自動的に行います。日本語、英語、中国語、韓国語に対応しているため、海外拠点での利用にもおすすめです。

「アイブリー」の導入により、簡単な問い合わせは自動回答できるため、電話対応件数を大幅に削減できます。さらに、迷惑電話対策や顧客管理機能、AIによる文字起こしなど、電話業務を便利にする機能が豊富にあり、月額3,317円~(年払いの場合/電話番号維持費除く)という低コストで利用可能。
クラウドPBXよりも手軽に導入できるため、海外に拠点を持つ企業におすすめの選択肢です。
※2025年11月1日、料金プランの月額料金およびサービス内容を改定させていただきました。今後もお客さまに安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。
料金プランの改定内容について詳しくは、下記のURLからご確認ください。

