カスハラはどこから?正当なクレームとの違いと企業の対応策
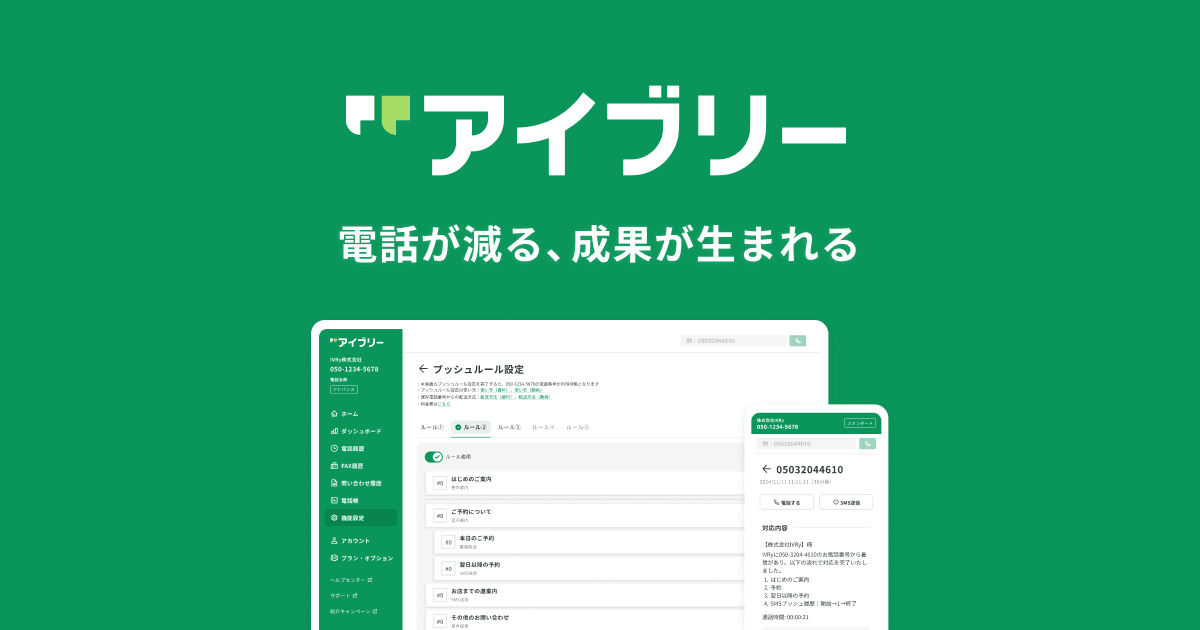
顧客からのクレームは、サービス改善の貴重な機会ですが、一線を越えた「カスタマーハラスメント(カスハラ)」は、従業員の心身を疲弊させ、企業の健全な運営を脅かす深刻な問題です。
「どこからがカスハラなのか」という判断基準が曖昧なために、現場の従業員が一人で問題を抱え込み、対応に苦慮するケースは少なくありません。
本記事では、正当なクレームとカスハラの明確な境界線、企業が取るべき法的対策、そして従業員を守り健全な職場環境を築くための具体的な対応策を、厚生労働省のガイドラインなどに基づき解説します。
どこからがカスハラなのか?
カスハラ問題の解決に向けた第一歩は、その定義を正しく理解し、社内で共通認識を持つことです。ここでは、カスハラの定義、正当なクレームとの違い、そして具体的な判断基準について解説します。
カスハラ(カスタマーハラスメント)の定義
厚生労働省は、カスハラを「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。
ここでのポイントは、要求の内容が妥当であったとしても、その伝え方(手段・態様)が社会常識から逸脱していれば、それはカスハラに該当するという点です。
クレームとの違いを理解する
正当なクレームとカスハラを分ける境界線は、要求を実現するための「手段・態様」が社会通念上、相当といえるかどうかにあります。
商品やサービスに対する意見や改善要求は、企業にとって貴重なフィードバックであり「正当なクレーム」です。
しかし、その要求を伝える際に暴言、脅迫、長時間の拘束、土下座の��要求といった手段が用いられれば、それは従業員の尊厳を傷つけ、就業環境を害する「カスハラ」となります。
カスハラかどうかの判断基準
現場で直面する事案がカスハラに該当するかどうかを客観的に判断するため、厚生労働省は以下の2つの基準を提示しています。
- 要求内容の妥当性 提供した商品やサービスに不備があったか、企業に過失はあったかなど、要求そのものに正当性があるかを判断します。
- 手段・態様の相当性 要求内容の妥当性に関わらず、その伝え方が社会的常識の範囲を逸脱していないかを判断します。大声での罵倒、威嚇、暴言、暴力、土下座の要求などは、それ自体が「社会通念上不相当」な行為と見なされます。
たとえ要求内容に正当性があったとしても、手段・態様が不相当であれば、その時点でカスハラに該当すると判断することが、従業員を守る上で非常に重要です。
カスハラに対する法的対策
カスハラへの対応は、単なる顧客サービスの問題ではなく、法的な義務とリスクを伴う経営課題です。企業が負うべき責任や、カスハラ行為者が問われうる罪について解説します。
弁護士が提供できるサポート
社内での対応が困難な場合、弁護士という外部の専門家によるサポートが有効です。
弁護士は、企業に対して法的な助言を行うだけでなく、代理人として顧客との交渉窓口になることも可能です。悪質��なケースでは、損害賠償請求や刑事告訴といった法的手続きも支援します。
平時から顧問弁護士と契約しておくことで、有事の際に迅速かつ的確な対応が期待できます。
カスハラの法的基準とその適用
企業は、労働契約法第5条に基づき、従業員が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」を負っています。
カスハラを放置したり、不適切な対応を取ったりした結果、従業員が精神疾患を発症した場合、企業はこの安全配慮義務違反を問われ、損害賠償を請求されるリスクがあります。
裁判では、マニュアルの整備や相談体制の構築など、企業が予防のために適切な体制を築き、それを誠実に運用していたかが厳しく問われます。
警察への相談・通報のタイミング
従業員や他の顧客の身体に危険が及ぶ場合や、業務に著しい支障が出ている場合は、ためらわずに警察へ通報すべきです。
具体的には、暴行・傷害、脅迫、器物損壊、退去要求に応じない(不退去)、大声で怒鳴り続ける(威力業務妨害)などの行為が見られた場合が該当します。
これらの行為はもはやクレームではなく犯罪行為であり、「お客様」としてではなく、犯罪行為者として法に則り冷静に対処する必要があります。
違法となるカスハラの具体例
顧客の言動がエスカレートし、社会のルールを逸脱した場合、それは違法行為、すなわち犯罪に該当する可能性があります。ここでは�、カスハラがどのような場合に犯罪となりうるのか、具体的な罪名と共に解説します。
不当な要求
商品やサービスに不備があったとしても、それに対する要求が常識の範囲を超えている場合は「不当な要求」と判断されます。
- 過大な金銭要求: 実際の損害額をはるかに超える慰謝料や賠償金の要求。
- 実現不可能な要求: 「社長を今すぐここに呼べ」といった、即時対応が物理的に不可能な要求。
- 義務のない謝罪の強要: 従業員個人への土下座や、謝罪文のWebサイトへの掲載要求。
これらの要求は、たとえ企業側に何らかの非があったとしても、正当な権利行使の範囲を逸脱しています。
脅迫や恐喝に該当する行為
相手に恐怖心を与える言動は、刑法上の「脅迫罪」や「恐喝罪」に問われる可能性があります。
- 脅迫罪: 「殺すぞ」「家に火をつける」「SNSでお前の個人情報を晒してやる」など、相手の生命、身体、財産、名誉に害を加えることを告知する行為。
- 恐喝罪: 脅迫を用いて金品や財産上の利益を要求する行為。
これらの発言がなされた時点で即座に対応を中止し、警察への通報を検討すべきです。
名誉毀損や威力業務妨害
企業の評判を不当に貶めたり、業務を妨害したりする行為も犯罪です。
- 名誉毀損罪・信用毀損罪: 公然の場で具体的な事実(真偽は問わな�い)を挙げて社会的評価を低下させる行為や、虚偽の情報を流して信用を傷つける行為。「あの店は腐ったものを売っている」とSNSに投稿するなどが該当します。
- 威力業務妨害罪: 大声で怒鳴り続ける、机を叩く、長時間居座るなど、威力を用いて正常な業務運営を妨害する行為。
- 侮辱罪: 「バカ」「死ね」など、事実を挙げずに公然と相手を侮辱する行為も該当します。
これらの行為は、企業の経済活動や従業員の尊厳を守るために、法的に対処すべき対象となります。
企業におけるカスハラ対策の重要性
カスハラ対策は、単に従業員を守るだけでなく、企業の持続的な成長にとっても不可欠な経営課題です。
従業員のメンタルヘルスと定着率
カスハラは、従業員の心身に深刻なダメージを与えます。精神的なストレスは、うつ病などの精神疾患や休職、離職の直接的な原因となり得ます。
従業員が安心して働ける環境を整備することは、人材の定着率を高め、採用や教育にかかるコストを削減することに直結します。カスハラ対策は、従業員のウェルビーイングを守るための「守りの施策」であると同時に、企業の根幹を支える人材を確保するための「攻めの投資」でもあるのです。
カスハラ対策が企業文化に与える影響
企業がカスハラに対して毅然とした方針を掲げ、組織として対応することは「会社は従業員を大切にする」とい��う明確なメッセージになります。
これにより、従業員は会社への信頼と帰属意識を高め、安心して業務に集中できるようになります。結果として、従業員一人ひとりのパフォーマンスが向上し、組織全体の生産性向上にも繋がります。
カスハラを許さない文化は、従業員が互いに尊重しあう、健全でポジティブな職場風土を醸成します。
企業の社会的責任とブランドイメージへの影響
カスハラ対策に積極的に取り組むことは、従業員の安全を守るという企業の社会的責任(CSR)を果たす上で不可欠です。
その姿勢を社外に明確に公表することは、顧客や取引先、投資家からの信頼を高め、企業ブランドのイメージ向上に貢献します。
逆に、カスハラへの対応が不十分だと「従業員を大切にしない企業」というネガティブな評判が広がり、ブランドイメージを大きく損なうリスクがあります。
カスハラへの具体的な対応策
実際にカスハラが発生した際に、現場が混乱せず一貫した対応を取れるようにするには、事前の準備が不可欠です。ここでは、具体的な対応策を3つのステップで解説します。
カスハラ発生時の初期対応
インシデント発生直後の対応が、その後の展開を大きく左右します。目標は、問題解決ではなく、状況の沈静化と正確な事実確認です。
- 冷静な傾聴: まずは相手の主張を遮らずに聞き、不満の内容を正確に把握します。
- 安易な謝罪を避ける: 事実関係が不明な段階で全面的に非を認める謝罪は避け、「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」など、相手の感情に寄り添う言葉に留めます。
- 複数名での対応: 必ず上司や他の従業員に協力を求め、一人で対応させないことを徹底します。これにより、対応者個人の負担を軽減し、客観的な証人を確保できます。
再発防止のための教育と研修
方針やマニュアルの策定だけでは不十分です。それらを全従業員に浸透させ、実践的なスキルとして身につけてもらうための教育・研修が不可欠です。
カスハラの定義や判断基準、対応フローといった知識の共有はもちろん、実際の場面を想定したロールプレイング研修を取り入れることが極めて効果的です。これにより、従業員は有事の際に自信を持って、冷静かつ適切な行動を取れるようになります。研修は正社員だけでなく、アルバイトを含む全ての従業員を対象に定期的に実施することが重要です。
社内向け対応マニュアルの整備
全従業員が参照できる、統一された対応マニュアルを整備します。これは、有事の際に従業員が迷わず一貫した行動を取るための「行動計画書」となります。
マニュアルには、以下の項目を盛り込むことが推奨されます。- 企業の基本方針- カスハラの定義と判断基準- 具体的な対応フロー(初期対応から警察への通報まで)- 報告・相談の手順と連絡先一覧- 報告書のテンプレート
厚生労働省が公開しているマニュアルなどを参考に、自社の実情に合わせて作成すると良いでしょう。
カスハラについてより詳しく知るには
カスハラ対策を進める上で、公的機関が提供する情報やリソースの活用は非常に有効です。ここでは、代表的なものをいくつかご紹介します。
関連法令やガイドラインの紹介
カスハラ対策の根幹となるのが、国や自治体が示す法令やガイドラインです。
- 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」: カスハラの定義から予防策、発生時の対応まで、企業が取るべき対策を網羅的に解説しています。具体的な事例や報告書の様式も含まれており、非常に実践的な内容です。
- 東京都「カスタマーハラスメント防止条例」: 2025年4月1日に施行された全国初の条例で、事業者の責務や都の支援策などが定められています。企業の取り組みを後押しする内容です。
参照: カスタマーハラスメント対策企業マニュアル | 厚生労働省 , 2021年 公開
参照: カスタマーハラスメント防止条例 | 東京都 , 令和7年4月1日施行
役立つツールや相談窓口
社内だけでなく、外部の専門機関やツールを活用することで、より実効性の高い対策が可能になります。
- 弁護士: 法的な判断が必要な場合や、悪質な行為が続く場合に相談します。顧問弁護士がいれば、迅速な対応が可能です。
- 警察: 暴行や脅迫など、犯罪行為に該当する場合は、ためらわずに通報します。非緊急時でも、最寄りの警察署の生活安全課が相談窓口となります。
- 通話録音・監視カメラ: 客観的な証拠を確保し、ハラスメント行為を抑止する効果が期待できます。導入する際は「録音・録画中」であることを明示するのが一般的です。
詳しくは「カスハラはどこに相談すれば良い?」をご覧ください。
厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団」
厚生労働省が運営するこのポータルサイトは、パワハラやセクハラだけでなく、カスハラに関する情報も豊富に提供しています。
マニュアルやリーフレットのダウンロード、研修動画の視聴、他社の取り組み事例の閲覧などが可能です。自社の対策レベルを客観的に把握し、さらなる改善のヒントを得るために定期的にチェックすることをおすすめします。
参照: あかるい職場応援団 | 厚生労働省 , 令和7年4月1日施��行
東京都の事業者ならカスハラ奨励金を適用できる場合も
東京都の事業者ならカスハラ奨励金を適用できる場合があります。(2025年9月24日募集再開)

東京都内の中小企業は、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策に関するマニュアルを整備した上で要件を満たすことで、奨励金(40万円)の受給を申請できます。
また、カスハラ対策として電話自動応答の「アイブリー」を対象プランを新規契約すると、受給要件のひとつである「AIを活用したシステム等の導入」として認められる場合があります。
この奨励金は「カスタマーハラスメント防止対策推進事業企業向け奨励金」と呼ばれるもので、事業者に東京都カスタマー・ハラスメント防止条例による措置を浸透させることを目的としています。
対象となる事業者は「常時雇用する従業員が300人以下の都内中小企業等」で、その他いくつかの要件を満たす必要があります。また、カスハラ対策に関するマニュアルの整備し、実践的な取り組みとして「録音・録画環境の整備」、「AIを活用したシステム等の導入」「外部人材の活用」のいずれかを実施している場合に限られます。
取り組みのひとつである「AIを活用したシステム等の導入」として、アイブリーの対象プランの新規契約を検討してみてはいかがでしょう。
まずはアイブリーのサービス資料をご覧いただき、担当者にご相談ください。
東京都カスハラ奨励金を利用するために
東京都のカスハラ奨励金を受給する要件のひとつとして、アイブリーの導入を適用できる可能性があります。アイブリーの各機能が電話応答でのカスハラ対策をサポートします。
ぜひ、アイブリーのサービス内容をわかりやすく解説した資料をご覧ください。
資料をダウンロード(無料)※奨励金の支給可否は、東京都の審査に基づき決定されます。申請要件の詳細は必ず公式サイトをご確認ください。
30着電まで無料
今すぐ試してみる料金や活用事例まで丸わかり
資料をダウンロードする料金プランについては下記からもご覧いただけます。
