カスタマーハラスメント(カスハラ)対応完全ガイド|企業の対策と実践マニュアル
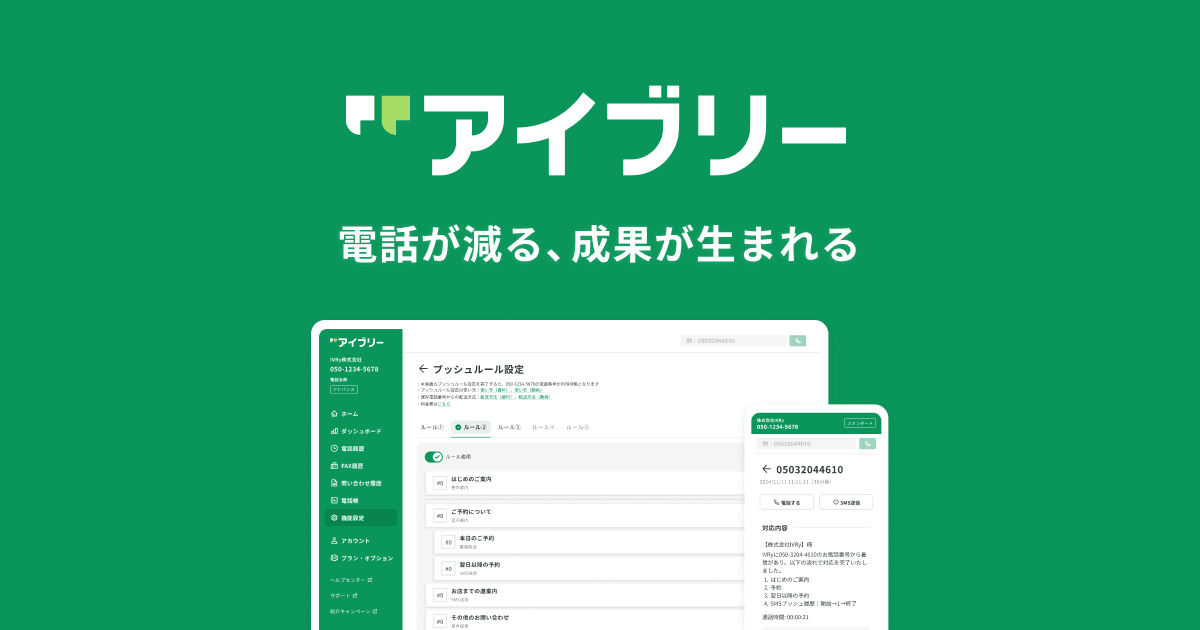
近年、顧客からの悪質なクレームや理不尽な要求、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」は、深刻な社会問題として認識されています。
従業員が心身ともに疲弊し、離職に至るケースも少なくありません。これは企業にとって、貴重な人材の損失だけでなく、サービス品質の低下や企業イメージの悪化にも直�結する重大なリスクといえるでしょう。
本記事では、カスハラの定義から、現場で実践できる具体的な対応策、企業として整備すべきマニュアルや法的知識について、解説します。
カスハラとは?
まず、カスハラ問題に取り組む上で基本となる、カスハラの定義や正当なクレームとの違いについて解説します。
カスハラの定義と背景
カスハラとは、顧客からのクレーム・言動のうち、その要求内容の妥当性に関わらず、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当であり、それによって従業員の就業環境が害されるものを指します。
かつて「お客様は神様」という考え方が存在し、従業員が理不尽な要求に耐えざるを得ない風潮もありました。しかし、従業員の心身の健康を脅かすこの問題に対し、社会の認識は大きく変化しています。
現在では、厚生労働省や東京都などがカスハラの定義を明確にし、企業に対して対策を講じるよう求めています。これは、カスハラがもはや単なる顧客サービス上の問題ではなく、企業の安全配慮義務に関わる労働問題として正式に位置づけられたことを意味します。
参照: カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル | 東京都 , 公開: 令和7年3月
正当なクレームとカスハラの違い
現場で最も判断に迷うのが、正当なクレームとカスハラの線引きです。両者の違いは、要求の「内容」と「手段・態様」という2つの軸で判断できます。
特性 | 正当なクレーム | カスタマーハラスメント(カスハラ) |
|---|---|---|
要求内容 | 商品の欠陥に対する交換や修理など、企業の過失に対する妥当な要求。 | 企業の責任範囲を超える過剰な要求(慰謝料、土下座の強要など)。 |
手段・態様 | 問題点を具体的かつ冷静に説明し、解決策を協議しようとする姿勢。 | 暴言、脅迫、威圧、人格否定、長時間の拘束など、社会通念上不相当な言動。 |
目的 | 問題の解決や原状回復。 | 感情のはけ口、ストレス発散、金銭や不当なサービスの要求など。 |
たとえ要求内容に正当性があったとしても、大声で怒鳴ったり、従業員を罵倒したりする行為は、その手段が社会通念上許容される範囲を超えており、明確にカスハラに該当します。
カスハラによる影響とリスク
カスハラを放置することは、従業員個人だけでなく、企業全体にも深刻な影響を及ぼします。ここでは、カスハラがもたらしうる具体的なリスクについて確認しておきましょう。
従業員への影響
カスハラの直接的なターゲットとなる従業員は、心身に大きなダメージを受けます。
精神的なストレスは、不安障害やうつ病といった精神疾患につながる可能性があります。また、仕事へのモチベーションが著しく低下し、最悪の場合、休職や離職に至ることもあるでしょう。
企業への影響
従業員の離職は、企業にとって計り知れない損失です。採用や教育にかけたコストが無駄になるばかりか、人材不足はサービス品質の低下を招きます。
さらに、カスハラが横行する職場環境は、他の従業員の士気をも下げ、組織全体の生産性を低下させるでしょう。SNSなどで悪評が拡散されれば、企業のブランドイメージが大きく損なわれるリスクもはらんでいます。
カスハラ対応の基本方針
カスハラから従業員を守り、企業としてのリスクを管理するためには、一貫した基本方針を定めることが不可欠です。ここでは、その基本方針を構築する上で重要な2つのポイントを解説します。
企業としての姿勢を明確にする
最も重要なのは、経営トップが「カスハラを断固として許さない」「従業員の安全を最優先する」という姿勢を明確に示すことです。
この方針は、社内規定やマニュアルに明記するだけでなく、ウェブサイトや店舗へのポスター掲示などを通じて社外にも公表することが有効です。これにより、悪質な要求に対する抑止力として機能すると同時に、従業員に「会社が守ってくれる」という安心感を与え、毅然とした対応を後押しします。
従業員一人で対応させない
カスハラ対応の鉄則は、従業員を一人で対応させないことです。
顧客が感情的になり始めた、あるいは不当な要求の兆候が見られた時点で、速やかに上司や他の従業員に助けを求め、複数名で対応する体制に切り替えることをルールとして徹底すべきです。
複数名で対応することで、従業員の心理的負担が軽減されるだけでなく、客観的な視点を保ち、より冷静な判断を下しやすくなります。
カスハラを未然に防ぐための準備
問題が発生してから対処するのではなく、発生そのものを防ぐための予防策も同様に重要です。ここでは、カスハラを未然に防ぐために企業が講じるべき準備を2点紹介します。
事前のマニュアル作成
実践的な対応マニュアルは、全従業員が共有すべき最も重要なツールです。マニュアルには、以下の項目を盛り込むことが推奨されます。
- 基本方針とカスハラの定義
- 具体的なケーススタディ(暴言、不当要求、時間拘束など)
- 対応フローチャート(対面・電話・メール別)
- 社内報告・エスカレーション体制
- 従業員のケアに関する手順
- 外部専門機関との連携基準
これらの内容を網羅し、誰が読んでも理解できる具体的な行動指針を示すことで、対応のばらつきを防ぎ、組織として一貫した行動を取ることが可能になります。
職員への教育と研修
マニュアルを作成するだけでなく、その内容を全従業員に浸透させるための教育と研修も不可欠です。
カスハラに関する知識を深める座学に加え、様々なシナリオを想定したロールプレイング研修を取り入れることは、きわめて効果的です。ロールプレイングを通じて、従業員は冷静な対応スキルを体得し、実際の場面でも自信を持って行動できるようになるでしょう。
カスハラ発生時の具体的な対応策
実際にカスハラが発生してしまった場合に、従業員が冷静かつ適切に行動するための具体的なステップを解説します。初期対応の質が、その後の事態の展開を大きく左右するといっても過言ではありません。
冷静に対応するためのステップ
相手が感情的であっても、まずは落ち着いて対応することが肝心です。
- 傾聴の姿勢を示す: まずは相手の主張を遮らずに最後まで聞きます。これは相手の要求を受け入れるという意味ではなく、冷静に事実を確認するための第一歩です。
- 安易に謝罪しない: 事実関係が不明な段階で全面的に謝罪することは避けるべきです。「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」など、相手の感情に対して限定的に謝罪するに留めましょう。
- 対応できること・できないことを明確に伝える: 企業のルールを超える不当な要求に対しては、「そのご要望にはお応えいたしかねます」と毅然とした態度で明確に断ることが重要です。
記録と証拠の重要性
後の社内検証や法的措置に備え、客観的な証拠を確保することは極めて重要です。
カスハラ対応においては、日時、場所、相手の発言内容、こちらの対応などを時系列で詳細に記録してください。可能であれば、相手に告知の上で会話を録音することも有効な手段となります。
電話対応の場合は「応対品質の向上のため、この通話は録音しております」といった自動アナウンスを導入することが、証拠確保とハラスメント抑止の両面で効果的です。
カスハラ対応のための心構え
カスハラに効果的に対処するためには、技術的な対応手順だけでなく、従業員自身の心構えやセルフケアも重要になります。ここでは、従業員が健全な精神状態を保ちながら業務にあたるためのポイントを解説します。
お客様との関係性の見直し
「お客様は神様」という考え方ではなく、「顧客と企業は対等な関係である」という認識を持つこと�が重要です。
企業は良質な商品やサービスを提供する責任を負いますが、それは従業員の人格や尊厳を犠牲にしてまで提供されるべきものではありません。顧客からの正当な意見や要望には真摯に耳を傾けつつも、理不尽な要求や人格攻撃に対しては、一人の人間として、また組織の一員として、毅然と立ち向かう権利があります。
この健全な境界線を意識することが、精神的な負担を軽減する第一歩となるのです。
ストレス管理とメンタルヘルス
カスハラ対応は、従業員にとって大きなストレスとなります。そのため、企業は従業員が一人でストレスを抱え込まないための仕組みを整える責任があります。
カスハラに遭遇した後は、上司が面談の機会を設け、従業員の感情に寄り添い、その労をねぎらうことが重要です。また、産業医や社外のカウンセリングサービス(EAP)など、専門家に相談できる窓口を設けて周知することも不可欠といえるでしょう。
従業員自身も、ストレスを感じた際には信頼できる上司や同僚に相談するなど、一人で抱え込まないことを意識しましょう。
カスハラに対する法的知識
カスハラ行為は、単なる迷惑行為に留まらず、刑法に触れる犯罪となる可能性があります。法的知識を持つことは、企業と従業員を守る上で強力な武器となります。
カスハラに関連する法律
カスハラの態様によっては、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
犯罪名 | 該当する行為の例 |
|---|---|
威力業務妨害罪 | 大声で怒鳴り続ける、何度も迷惑電話をかけるなどして、正常な業務を妨害する行為。 |
脅迫罪 | 「殺すぞ」「SNSで晒してやる」など、生命、身体、名誉、財産に害を加えることを告知する行為。 |
強要罪 | 脅迫や暴行を用いて、土下座や金品の提供など、義務のないことを無理やり行わせる行為。 |
不退去罪 | 店舗などから退去するように求められたにもかかわらず、居座り続ける行為。 |
暴行罪・傷害罪 | 従業員を殴る、物を投げつけるなど、身体に危害を加える行為。 |
これらの知識は、不当な行為に対して「その行為は〇〇罪にあたる可能性があります」と警告し、相手を牽制する材料にもなり得ます。
専門機関へ相談すべきタイミングの判断基準
社内での対応が困難、または危険が伴うと判断した場合は、躊躇なく外部の専門機関に相談すべきです。
相談先 | 相談・通報を検討すべきタイミング |
|---|---|
弁護士 | ・高額な慰謝料など、不当な金銭要求をされた場合 |
警察(#9110) | ・緊急性はないが、犯罪に発展する可能性があり、今後の対応を相談したい場合 |
警察(110番) | ・暴力行為や器物損壊、明確な脅迫など、身の危険が差し迫っている場合 |
特に、従業員の身の安全が脅かされる状況では、ためらわずに110番通報することが最優先です。マニュアルにこれらの基準を明記し、従業員が判断に迷わず行動できるよう支援することが重要です。
AIでカスハラ対策ができる?
カスハラ対策は、社会全体の意識の変化とともに、テクノロジーの活用など新たなステージに進んでいます。
テクノロジーの活用
AIなどのテクノロジーは、カスハラ対策において大きな可能性を秘めています。
例えば、AIを活用した音声認識システムは、通話内容から顧客の感情(怒りなど)やカスハラの兆候となるキーワードを検知し、管理者にアラートを送ることが可能です。これにより、問題が深刻化する前に介入できます。
また、簡単な問い合わせにはAIチャットボットが一次対応することで、有人対応の負担を軽減し、従業員がより複雑で専門的な業務に集中できる環境を整えることも、カスハラのリスクを間接的に低減させる上で有効です。
東京都の事業者ならカスハラ奨励金を適用できる場合も
東京都の事業者ならカスハラ奨励金を適用できる場合があります。(2025年9月24日募集再開)

東京都内の中小企業は、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策に関するマニュアルを整備した上で要件を満たすことで、奨励金(40万円)の受給を申請できます。
また、カスハラ対策として電話自動応答の「アイブリー」を対象プランを新規契約すると、受給要件のひとつである「AIを活用したシステム等の導入」として認められる場合があります。
この奨励金は「カスタマーハラスメント防止対策推進事業企業向け奨励金」と呼ばれるもので、事業者に東京都カスタマー・ハラスメント防止条例による措置を浸透させることを目的としています。
対象となる事業者は「常時雇用する従業員が300人以下の都内中小企業等」で、その他いくつかの要件を満たす必要があります。また、カスハラ対策に関するマニュアルの整備し、実践的な取り組みとして「録音・録画環境の整備」、「AIを活用したシステム等の導入」「外部人材の活用」のいずれかを実施している場合に限られます。
取り組みのひとつである「AIを活用したシステム等の導入」として、アイブリーの対象プランの新規契約を検討してみてはいかがでしょう。
まずはアイブリーのサービス資料をご覧いただき、担当者にご相談ください。
東京都カスハラ奨励金を利用するために
東京都のカスハラ奨励金を受給する要件のひとつとして、アイブリーの導入を適用できる可能性があります。アイブリーの各機能が電話応答でのカスハラ対策をサポートします。
ぜひ、アイブリーのサービス内容をわかりやすく解説した資料をご覧ください。
資料をダウンロード(無料)※奨励金の支給可否は、東京都の審査に基づき決定されます。申請要件の詳細は必ず公式サイトをご確認ください。
30着電まで無料
今すぐ試してみる料金や活用事例まで丸わかり
資料をダウンロードする※2025年11月1日、料金プランの月額料金およびサービス内容を改定させていただきました。今後もお客さまに安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。
料金プランの改定内容について詳しくは、下記のURLからご確認ください。
