ビジネスフォンメーカー6社を徹底比較!選び方や価格も
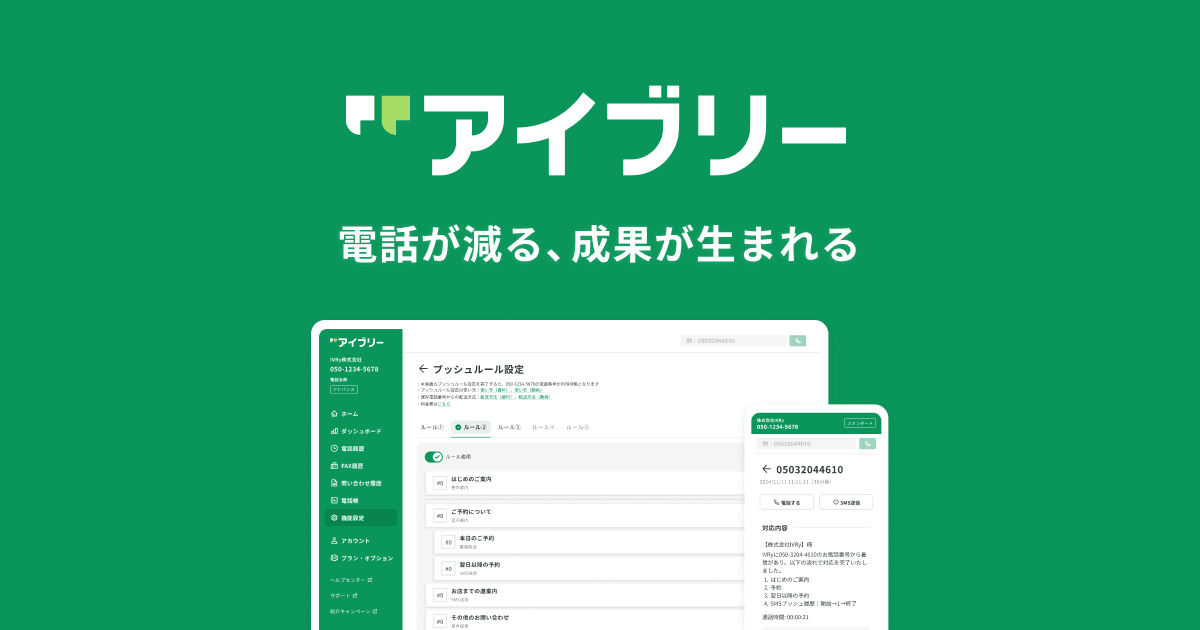
オフィスの新設や移転に伴い、「自社の規模に合ったビジネスフォンはどれか」「導入や運用にどれくらいの費用がかかるのか」「どんな機能があれば業務が効率化するのか」など、悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
ビジネスフォンは単なる電話機ではなく、企業のコミュニケーション基盤を支え、生産性を左右する戦略的なツールといえます。本記事では、中小企業のオフィスに最適なビジネスフォンの選び方から、主要メーカーのおすすめ機種、導入にかかるコストについて、解説します。
�ビジネスフォンの選び方
最適なビジネスフォンを選ぶためには、まず自社の状況を正しく把握することが重要です。ここでは、ビジネスフォンを選ぶ際に必ずチェックしておきたい3つのポイントをご紹介します。
導入目的に応じた選び方
なぜビジネスフォンを導入するのか、その目的を明確にすることが最初のステップです。「顧客からの問い合わせ対応をスムーズにしたい」「社内のコミュニケーションを活性化させたい」「営業活動の効率を上げたい」など、目的によって必要な機能や最適なシステムは大きく異なります。
目的が明確になれば、数ある選択肢の中から自社に本当に必要なものだけを効率的に選び出せます。
必要な機能を見極める
ビジネスフォンには基本的な通話機能以外にも、業務効率を高めるための様々な機能が搭載されています。
例えば、担当者不在時に他の電話へ自動で着信を転送する「転送機能」 や、かかってきた電話を一旦保留にして別の担当者が受けられる「保留機能」 は、ほとんどのビジネスフォンに備わっている基本的な機能です。
さらに、かかってきた電話番号からPC画面に顧客情報を表示する「CTI連携」 、自動音声ガイダンスで着信を振り分ける「IVR機能」 、コンプライアンス強化や応対品質向上に役立つ「通話録音機能」 といった、より高度な機能も存在します。導入目的と照らし合わせ、自社にとって費用対効果の高い機能を見極めましょう。
詳しくは「ビジネスフォンで何ができる?機能の概要と業務への貢献を詳しく解説」をご覧ください。
予算に応じた選択肢
ビジネスフォンの導入には、機器の購入や設置工事にかかる「初期費用」 と、月々の回線利用料や保守費用などの「ランニングコスト」 が発生します。
伝統的なオフィス内に交換機を設置する「オンプレミス型」は初期費用が高額になる傾向がある一方、クラウド上で機能を利用する「クラウドPBX」は初期費用を大幅に抑えることが可能です。
目先の初期費用だけでなく、数年にわたる運用コストまで含めた総所有コスト(TCO)を算出し、自社の予算に合った無理のない選択をすることが重要です。
ビジネスフォンメーカーのシェアとおすすめランキング
どのメーカーのビジネスフォンが多くの企業に選ばれているのかを知ることは、メーカー選定における重要な指標となります。客観的なデータとして国内市場のシェアを把握し、自社のニーズと照らし合わせることで、信頼性の高いメーカーを選びやすくなります。
国内のビジネスフォン市場では、長年の実績と信頼からNTTが約40%とトップシェアを誇っています。次いで、中小企業向けに強みを持つSAXA、大企業やコールセンターでの実績が豊富なNECなどが続いています。
ここでは、市場シェアや各メーカーの強みを基に、おすすめのビジネスフォンメーカーをランキング形式でご紹介します。
順位 | メーカー | シェア・特徴 | こんな企業におすすめ |
|---|---|---|---|
1位 | NTT | 国内シェアNo.1(約40%)。圧倒的なブランド力と全国を網羅するサポート体制が強み。 | 安定運用と手厚いサポートを最優先し、ブランドの信頼性を重視する企業。 |
2位 | NEC | 大規模システムでの豊富な実績に裏打ちされた高い技術力。企業の成長に合わせた柔軟な拡張性を持つ。 | 将来的な人員増や拠点展開を計画している成長企業や、複数の拠点を持つ企業。 |
3位 | SAXA | 中小企業向け市場に特化し、優れたコストパフォーマンスを実現。ユニークな付加価値機能も魅力。 | コストを抑えつつ、スマートフォン連携など高機能なシステムを導入したい企業。 |
おすすめのビジネスフォンメーカー6選
国内のビジネスフォン市場は、長年の実績と信頼を誇るメーカーによって形成されています。ここでは、主要メーカーとその特徴、中小企業におすすめの代表的な機種をご紹介します。
メーカー | 特徴 | こんな企業におすすめ |
|---|---|---|
NTT | 圧倒的なブランド力と全国を網羅するサポート体制が強み。流通量が多く、保守性に優れる。 | 安定運用と手厚いサポートを最優先し、ブランドの信頼性を重視する企業。 |
NEC | 大規模システムでの豊富な実績に裏打ちされた高い技術力。企業の成長に合わせた柔軟な拡張性を持つ。 | 将来的な人員増や拠点展開を計画している成長企業や、複数の拠点を持つ企業。 |
SAXA | 中小企業向け市場に特化し、優れたコストパフォーマンスを実現。ユニークな付加価値機能も魅力。 | コストを抑えつつ、スマートフォン連携など高機能なシステムを導入したい企業。 |
Panasonic | 家電で培った信頼のブランド力と、多彩な機能、耐久性の高い設計が特徴。 | 知名度のあるブランドで、長期間安心して使える堅牢なシステムを求める企業。 |
IWATSU | 高品質な音声通話に定評があり、音声コミュニケーションを重視する業務に向いている。 | 金融やコンサルティングなど、クリアな音声での対話が特に重要な業務を行う企業。 |
NAKAYO | リーズナブルな価格設定と、誰でも直感的に使えるシンプルな操作性が魅力。 | コストを最優先し、必要最低限の機能でシンプルな運用をしたい企業。 |
NTTのビジネスフォン
「電話といえばNTT」といわれるほどの高い知名度と信頼性が最大の強みです。全国に広がるサポート網により、どこにオフィスを構えても迅速な対応が期待できます。最新の「SmartNetcommunity αZX II」シリーズは、スマートフォン連携やクラウドサービスとの連携にも対応しており、現代的な働き方をサポートします。
NECのビジネスフォン
大企業から中小企業まで、あらゆる規模に対応できる柔軟な拡張性がNECの強みといえるでしょう。主装置をユニット式にすることで、事業の成長に合わせて無駄なくシステムをスケールアップできます。「UNIVERGE Aspire」シリーズは、多拠点の内線化やテレワーク対応機能が強力で、企業の成長戦略を力強く支えます。
SAXAのビジネスフォン
中小企業に特化することで、高い技術力とコストパフォーマンスを両立しています。「PLATIA Ⅲ」シリーズに搭載されている高機能なスマートフォン連携アプリ「MLiner」は、多くの企業から高く評価されています。また、防水・防塵仕様の電話機や、人感センサーと連携したセキュリティ機能など、現場のニーズに応えるユニークな機能も提供しています。
Panasonicのビジネスフォン
長年培ってきたブランドイメージによる信頼感と、多彩な機能を搭載しつつ、ユーザーが使いやすいインターフェースを追求しており、様々なビジネスシーンで高いパフォーマンスを発揮します。ただし、現在パナソニックは自社での新規開発は行わず、他社メーカーのOEM製品を主力としています。そのため、機種選定の際は製造元メーカーの技術力や特徴も考慮に入れると良いでしょう。
IWATSUのビジネスフォン
岩崎通信機(IWATSU)は、クリアで高品質な音声通話技術に強みを持ちます。独自の機能を搭載したモデルも多く、特定の業界に特化した製品も展開。音声品質を何よりも重視する企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。
NAKAYOのビジネスフォン
ナカヨは、コストパフォーマンスに優れた製品ラインナップで知られています。特に、専門的な知識がなくても直感的に操作できるシンプルなインターフェースは、IT担当者がいない中小企業にとって大きなメリットといえるでしょう。基本的な機能をしっかり押さえつつ、導入・運用コストを最小限に抑えたい場合に最適です。
ビジネスフォンのメリットとデメリット
多くの企業で利用されているビジネスフォンですが、導入を検討する上ではメリットとデメリットの両方を正しく理解しておくことが大切です。
ビジネスフォンのメリット
ビジネスフォンの最大のメリットは、複数の外線と内線を効率的に共有・管理できる点にあります。これにより、複数の社員が同時に外線通話を行ったり、社員同士で無料の内線通話を行ったりすることが可能です。
また、保留転送やグループ着信、通話録音といったビジネスに特化した機能は、顧客対応の品質向上と業務の効率化に大きく貢献します。適切に活用することで、ビジネスチャンスの拡大やコスト削減にも繋がるでしょう。
ビジネスフォンのデメリット
一方で、デメリットも存在します。特に、オフィスに物理的な機器を設置するオンプレミス型の場合、主装置や電話機の購入、設置工事などで高額な初期費用がかかることがあります。
また、システムの運用や設定変更にはある程度の専門知識が求められるため、IT担当者がいない企業にとっては負担になる可能性も否めません。故障時の対応も、迅速なサポート体制がなければ業務に支障をきたすリスクとなります。
【利用者の声】リモートでも対応できるビジネスフォンで「自分の仕事に専念」
『弥生会計』などのパッケージソフト連携商品を販売するOWL合同会社では、技術者が自宅で作業をし、遠隔操作で顧客のサポートを実施しています。そのなかで代表電話番号にかかってくる電話と、既存顧客のサポート電話を一本化したいと考え、アイブリーを導入しました。
これにより、営業電話に出る必要がなくなるとともに、オフィスに出社しなくても問い合わせや顧客のフォローに集中できるようになったといいます。
OWL合同会社
営業統括
スタッフは、 ほぼ全員がエンジニアなので、営業電話がかかってきても答えられません。それに私たちの仕事はBtoBですし、対応が不要な電話への返信は減らして、自分の仕事に専念できるように希望していました。
ですから、それが叶ってありがたいです。
リモートでも利用できるビジネスフォンとしての使い方と、AIが用件を聞くAI電話としての使い方とをうまく併用している例といえそうです。
ビジネスフォンの機能比較
ビジネスフォンの導入を成功させる鍵は、自社のニーズに合ったシステム形態を選ぶことです。ここでは、特に重要な比較ポイントとなる「クラウド型」と「オンプレミス型」の違いについて解説します。
クラウド型とオンプレミス型の違い
ビジネスフォンのシステムは、心臓部であるPBX(電話交換機)をどこに置くかによって、大きく「クラウド型」と「オンプレミス型」に分かれます。この違いを理解することが、最適なシステム選びの鍵を握ります。
項目 | クラウドPBX(クラウド型) | ビジネスフォン |
|---|---|---|
PBXの場所 | インターネット上(データセンター) | 自社オフィス内 |
初期費用 | 低い(0円〜数万円) | 高い(数十万〜数百万円) |
導入スピード | 速い(最短即日〜) | 遅い(数週間〜数ヶ月) |
運用・保守 | ベンダー任せで手間いらず | 自社での管理・保守が必要 |
拡張性 | 高い(Web上で簡単に追加・削除) | 低い(物理的な工事が必要) |
働き方 | 柔軟(スマホ連携でテレワーク対応) | オフィス中心 |
ランニングコスト | 月額利用料が発生 | 保守費用・電気代などがかかる |
オンプレミス型 は、自社に物理的な主装置を設置する従来からある方法です。初期投資は高額になりがちですが、自社の要件に合わせて細かくカスタマイズでき、インターネット回線の状況に左右されない安定した通話品質が魅力です。
対照的にクラウドPBX は、インターネット経由でPBX機能を利用するサービスです。物理的な機器が不要なため初期費用を大幅に削減でき、導入もスピーディに行えます。スマートフォンを内線化してテレワークに対応したり、事業規模の拡大・縮小に柔軟に対応できたりと、現代的な働き方にマッチしています。
詳しくは「クラウドPBXとは?電話DX実現のヒントとなる特徴やメリットなどを解説!」をご覧ください。
クラウドPBXも選択肢に入れよう
かつてビジネスフォンといえばオンプレミス型が主流でしたが、現在ではクラウドPBXが中小企業にとって極めて有力な選択肢となっています。
初期費用を抑えて迅速に電話環境を構築したい、従業員のテレワークを推進したい、将来の事業拡大に備えて柔軟なシステムを導入したい、といったニーズを持つ企業にとって、クラウドPBXは多くの課題を解決してくれるでしょう。オンプレミス型に固執せず、クラウドPBXも必ず比較検討の対象に加えることをお勧めします。
ビジネスフォンの価格・費用相場
ビジネスフォンの導入を検討する上で、最も気になるのが「価格」ではないでしょうか。ビジネスフォンの価格は、機器の購入や工事にかかる「初期費用」と、月々の利用料などの「ランニングコスト」で構成されています。
導入形態(オンプレミス型/クラウド型)や事業規模、必要な機能によって費用は大きく変動するため、それぞれの内訳と相場を正しく理解し、自社の予算に合った計画を立てることが不可欠です。
初期費用の内訳と相場
初期費用は、主に「機器代」と「工事・設定費」で構成されます。特にオンプレミス型の場合は、心臓部である主装置(PBX)が高額になる傾向があります。
項目 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
主装置(PBX) | 数十万円~数百万円 | 接続する電話機の台数や回線数によって変動。 |
電話機本体(1台) | 新品: 1.5万~5万円 | 機種や機能によって異なる。 |
設置工事・設定費 | 10万円~ | 配線工事、システム設定など。オフィスの規模による。 |
一方で、クラウドPBXの場合、物理的な主装置や大規模な配線工事が不要なため、初期費用を0円〜数万円程度に大幅に抑えることが可能です。
ランニングコストの内訳と相場
ランニングコストは、月々継続的に発生する費用です。オンプレミス型とクラウド型で主な内訳が異なります。
項目 | オンプレミス型 | クラウドPBX |
|---|---|---|
基本料金 | 回線利用料 | サービス利用料(ID数に応じる) |
通話料 | 使った分だけ | 使った分だけ(プランにより無料通話分がある場合も) |
保守費用 | 必須(機器のメンテナンス) | 不要(サービス料に含まれる) |
クラウドPBXは月額利用料が発生しますが、保守費用が不要な点や、通話料が比較的安価な傾向にある点を考慮すると、総所有コスト(TCO)で有利になるケースが多くあります。
導入・運用コストを抑えるポイント
高額なイメージのあるビジネスフォンですが、いくつかのポイントを押さえることで、導入・運用コストを賢く抑えることができます。
- クラウドPBXを活用する: 何度も触れている通り、初期費用を劇的に削減できる最も効果的な方法です。
- リース契約を検討する: 機器を購入するのではなくリースにすることで、初期費用を平準化できます。ただし、総支払額は購入より高くなる点に注意が必要です。
- 中古品を視野に入れる: 機器代を数分の一に抑えられますが、保証がなく故障リスクがあることを理解しておく必要があります。
- 相見積もりを徹底する: 同じ条件で複数の業者から見積もりを取り、価格やサービス内容を比較検討することは必須です。価格交渉の材料にもなります。
- 必要最低限の機能・台数から始める: 最初から多機能・大規模なシステムを導入するのではなく、自社の業務に本当に必要なものだけを見極め、スモールスタートを切ることも重要です。
AIが応答!30着電まで無料
今すぐ試してみるAI電話で業務改善
資料をダウンロードするビジネスフォンの導入前に確認すべきポイント
導入を決定する前に、費用や工事に関する具体的なポイントを確認しておけば、後のトラブルを未然に防げます。
初期費用の内訳
初期費用は主に「機器代」と「工事・設定費」で構成されます。オンプレミス型の場合、主装置と電話機本体の費用に加え、配線工事やシステム設定のための技術料が発生します。見積もりを取る際は、何にいくらかかるのか、内訳を詳細に確認することが重要です。
月額費用の計算方法
ランニングコストとしては、NTTなどに支払う「回線利用料」や「通話料」に加え、オンプレミス型の場合は「保守費用」、クラウド型の場合は「サービス利用料」がかかります。特にクラウドPBXはプランやオプションが多彩なため、自社に必要な機能が含まれているか、将来的にユーザーが増えた場合の料金体系はどうなるかなどを細かくシミュレーションしておきましょう。
工事期間と��準備物
オンプレミス型の導入には、主装置の設置や配線工事が伴います。オフィスの規模にもよりますが、契約から利用開始まで数週間から1ヶ月以上かかることもあります。移転や新設のスケジュールに合わせて、早めにベンダーと打ち合わせを開始することが肝心です。工事当日にスムーズに作業が進むよう、設置場所の確保など、必要な準備についても事前に確認しておきましょう。
ビジネスフォンに関するよくある質問
Q. 主要メーカーはどこですか?NTT以外の選択肢はありますか?
A. 国内シェアではNTTがトップですが、NEC、SAXA、IWATSU、NAKAYOなども高い実績を持つ主要メーカーです。それぞれ大企業向け、中小企業向け、あるいは特定の業界向けなど強みが異なります。自社の規模や業種に合ったメーカーを選ぶことが重要です。
Q. 導入にかかる設置費用はどれくらいですか?
A. 導入形態によって大きく異なります。クラウドPBXであれば数万円程度に抑えられますが、オフィス内に機器を設置するオンプレミス型の場合は、配線工事費などで10万円以上かかることも珍しくありません。オフィスの規模や導入する機器によって変動するため、必ず業者に見積もりを依頼しましょう。
Q. 今使っている電話番号はそのまま使えますか?
A. 「番号ポータビリティ」という制度を利用すれば、多くの場合で現在利用中の電話番号を引き継ぐことが可能です。ただし、番号の種類や契約状況によっては引き継げないケースもあるため、契約前に必ず利用中の電��話会社と導入予定のベンダーの両方に確認してください。
※2025年11月1日、料金プランの月額料金およびサービス内容を改定させていただきました。今後もお客さまに安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。
料金プランの改定内容について詳しくは、下記のURLからご確認ください。
